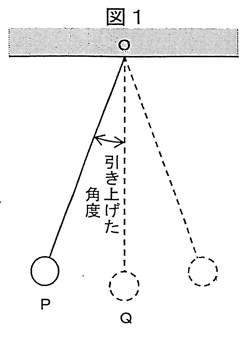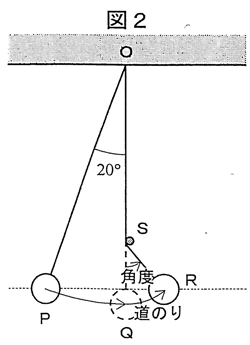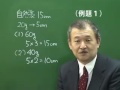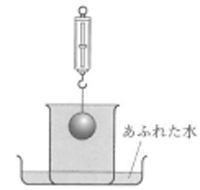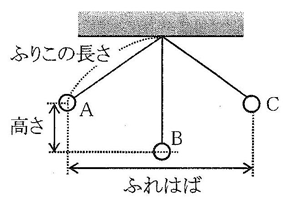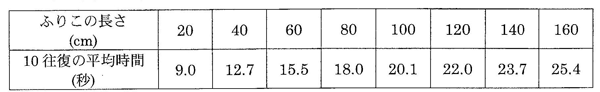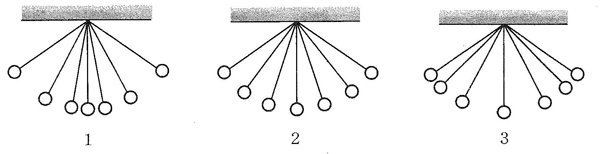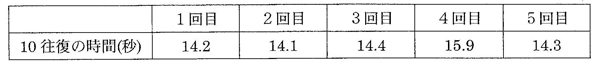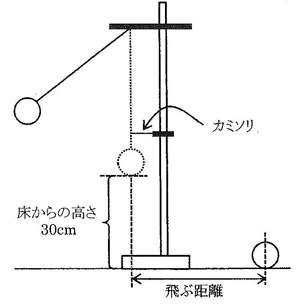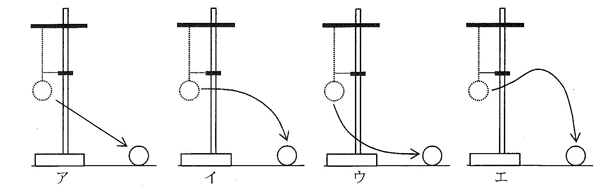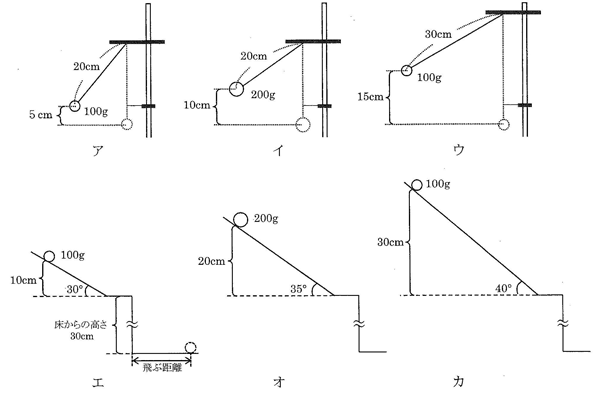2017年桜蔭中学の問題です。
図1のように.重さの無視できる糸のはしにおもりをつけ、もう一方のはしを天じょうの点Oに固定してふりこを作り、以下の実験を行いました。下の問いに答えなさい。
〔実験〕 表1のA~Gのように条件を変えてふりこの実験を行った。
おもりを自然に垂らした位置Qから.糸を張ったままある角度引き上げた位置Pで手をはなし、10往復してもとの位置Pにもどるまでの時間を調べた。
表1

問1(a)おもりの重さ、(b)はじめに引き上げた角度、(c)ふりこの長さをそれぞれ大きくしたとき、ふりこが10往復するのにかかる時間はどのようになりますか。つぎのア~ウから選び、記号で答えなさい。また、それらのことは、A~Gのうちのどの2つを比べることによってわかりますか。それぞれA~Gの記号の組み合わせで答えなさい。
ア.長くなる イ.変わらない ウ.短くなる
問2 A~Gのうち、Qを通るときのおもりの速さが最も速いのはどれですか。
問3 図2のように、200gのおもりをつけた120cmのふりこの、支点Oから90cm真下の位置Sに棒を固定し、おもりを20°引き上げた位置Pで手をはなしました。おもりは最も低い位置Qを通り、Pと同じ高さの位置Rまで達しました。Sを中心とするQからRまでの角度は.どのような角度でしょうか。また.おもりが通るQからRまでの道のりはどのような長さでしょうか。それぞれつぎのア~カから選び.記号で答えなさい。
ア.20°より小さい イ.20°である う.20°より大きい
エ.道のりQRは、道のりPQよりも短い
オ.道のりQRは、道のりPQと等しい
力.道のりQRは、道のりPQよりも長い
問4 問3のとき、ふりこをはなしてから10往復してPにもどってくるまでにかかる時間は何秒ですか。
【解説と解答】
問1
(解答)
おもりの重さ、引き上げた角度は関係なく、ふりこの長さが長ければ周期は長くなります。
また比較する対象以外の条件をすべて同じにしないと対照実験にはなりません。
(a) 時間イ 実験の組み合わせ C・E
(b) 時間イ 実験の組み合わせ A・C
(c) 時間ア 実験の組み合わせ A・B
問2
ふりこの長さが一番長く、引き上げた角度が一番大きいものがQで最も速くなります。
(解答)G
問3
ふりこの長さが短くなるので、角度は大きくなります。またQRの方がPQよりも短くなります。
(解答)角度ウ 道のり エ
問4
長さが30cmになるのは120cmの4分の1ですから、周期は2分の1になります。したがって11秒。その半分ですから5.5秒。
90cmは22秒ですから、その半分で11秒。5.5+11=16.5秒
(解答)16.5秒
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
2年でも長いが
6年生の教室から
とにかく読み込もう
今日の慶應義塾進学情報
2月5日、6日