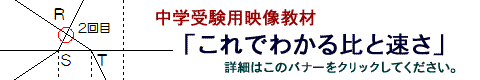最近の中学入試の国語の問題文は、なかなか難しい。
高校入試の現代文と比べてもそんなに変わりがありません。これはある意味仕方のないところがあるのです。というのは、小学生用に書かれた文章というのは、非常に数が少ない。物語文もやはり大人向けに書かれたものが多いわけですから、入試問題を作ろうと思って採録すると、まあ、やはり難しい文章になってしまいやすいのです。
で、文章を読んでいると、当然のことながら、子どもたちが知らない言葉が出てきます。つまり、語彙が不足しているわけですが、これを補うのにどうすればいいでしょうか。
まず国語の読解の練習をするときは、お父さんかお母さんか、どちらかがいっしょに勉強してあげるのが望ましい。一緒に読んであげて、「これはわからないかな」と思う単語の意味はどんどん教えます。辞書で解決しようとしてはいけません。というのは国語の辞書の場合Aということばを調べてBということばが出てくる。これでわかればいいが、Bということばがわからない。それでこれを調べてみると今度はAと書いてあることがあるのです。子どもでは解決できない。だから大人が教えてあげる。これは調べさせないで、どんどん教える。上手な説明である必要はありません。いろいろなことばを使って説明してあげれば良いのです。これが一番、語彙が増えます。
なぜか?
お父さん、お母さんと普段使わないことばを使って会話をしているからです。子どもは言葉を耳から習います。小さい時は文字を知らないのだから、すべて耳から習う。耳から入ってくることばと物のイメージでむすびつけて覚える。だから耳から入る情報が一番覚えやすいのです。
成長するにつれて文字から覚えることも多くなるが、言葉は耳から入ると良く覚えます。だから方言もわかるし、女子高生の流行語も耳から入ってきてみんな覚えている。
だから大人と会話をすればするほど、子どもの語彙は増えるのです。子どもたち同士の会話ではあまり増えない。お互いわかる言葉でしか話さないから、語彙が増えないのです。昔は同じ家に多くの大人がいたから、会話をすることも多かったので言葉を覚えるのが早かった。今はお父さん、お母さんとすらなかなか話ができないから、子どもたちの言葉が増えないのです。
耳から入るのなら、テレビはどうか?といえば、もちろんある程度の効果はありますが、テレビは双方向ではないので、子どもが一方的に聞いているだけだから、会話に比べれば落ちます。言葉は使うから覚えるので、使わなければどんどん忘れる。小さい時に海外にいて英語がしっかりしゃべれていた子が日本に戻ってきてしゃべれなくなるのも同じ理由です。
ということで、そろそろ冬休み。受験生は追い込みですが、子どもたちにとっては楽しいクリスマス、正月と続きます。子どもたちがたくさんお父さん、お母さんや大人の人たちと話す機会ですから、大切にしてください。
==============================================================
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
ほめる学校
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
12月23日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数4年後期第19回 算数オンライン塾「まとめのテスト」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================
![]()
にほんブログ村


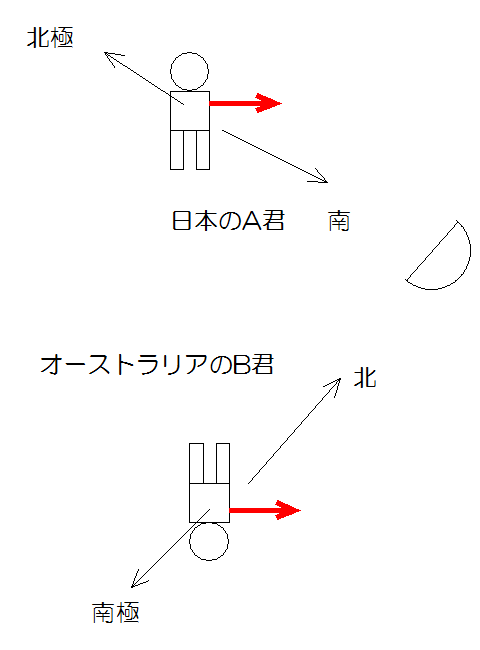
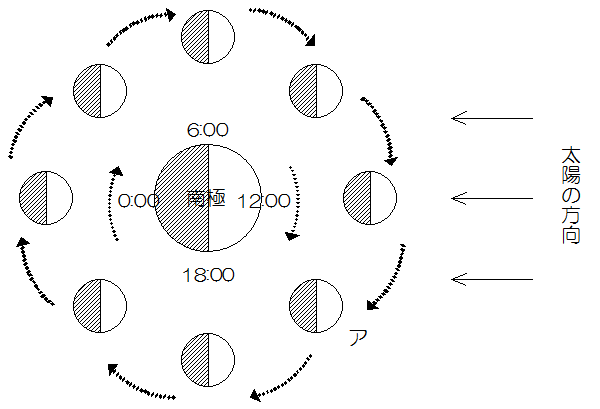

 図1
図1 図2
図2