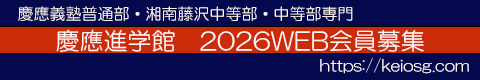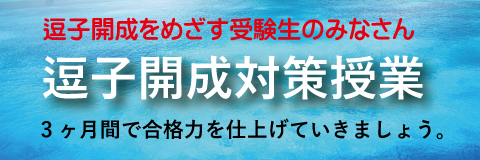この時期になると、そろそろやっている問題はもう、入試まで当たらないという可能性があります。ここでやって、次にお目にかかるのは入試ということになるとすれば、ここでしっかり理解できていればいいが、そうでなければ、やったことがあるなあ、ぐらいで試験を受けることになる。
入試問題を見た後、子どもたちに、
「この問題はやったよね。」というと、
「え、やったっけ?」と言われて、良くがっかりしたものですが、しかし、これはよくあることなのです。
つまり入試で出る問題は塾でも良く研究しているから、確かに塾でやった問題が入試で出る場合はあるわけですが、それができない、ということは非常にもったいない。
だから、今は復習が大事なのです。
一応取り組んだのだから、どうせやるのなら、次にこれが出ても絶対にできる、というような自信をもてるように練習してほしいのです。
復習するときに、これは次にできるかどうか?と自分に問いかけてみる。
まだ充分でないな、と思ったら、もう一回やってみるのも大事でしょう。
そんなことをしていたら、時間が足りなくなるかもしれません。
しかし、全部が中途半端であるよりは、これだけは大丈夫、というようにしていった方が良いのです。
この時期は復習の精度を上げることが大切です。
これをやるのは、もうこれで最後だ、という意識を持っていれば、多少なりとも結果は違ってきます。
次に出されても絶対できる、という自信をぜひ培って行きましょう。
10月23日の問題(立体図形の問題)
1週間無料公開されています。