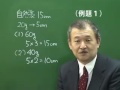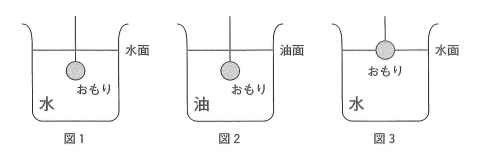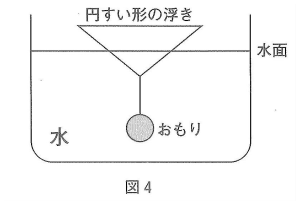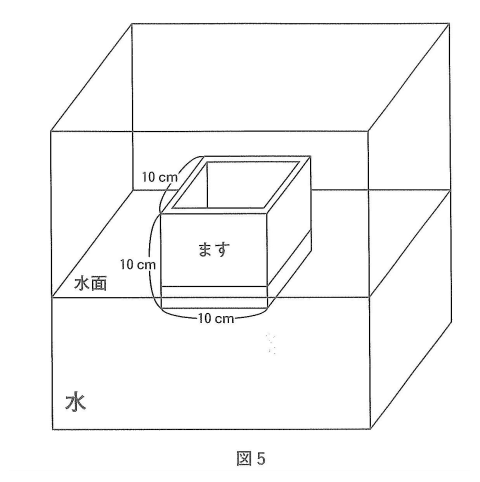2015年駒場東邦の問題です。
(1)図1のように、太さがどこでも同じ鉄の棒(長さ30cm)の両はしの点あ、いに、それぞれ軽くて細い(重さと体積を考えなくてよい)ひもで、鉄のおもりA(重さ55g、体積7cm3)と鉄のおもりB(重さ110g、体積14cm3)をつり下げ、点うを軽くて細いひもでつるしたところ、棒は水平になって静止しました。点うから棒の中心の点えまでの長さは、3cmでした。なお、棒の重さは、点えにかかると考えてよいものとします。
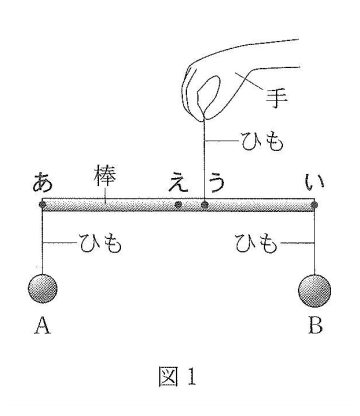
1) 棒の重さは、何gですか。
2) 手がひもを引く力の大きさは、何gですか。
3) 棒の体積は、何cm3ですか。
(2)水中の物体には、その物体が押しのけた水の重さに等しい大きさの上向きの力(浮力)がはたらきます。浮力は物体の中心の点(重さがかかる点と同じ点)にかかります。また、水1cm3の重さは1gです。さて、棒を水平に保つように手で支えながら、おもりA、Bをゆっくりと水そうの水の中に入れ、そっと手をはずし、図2の状態にしました。
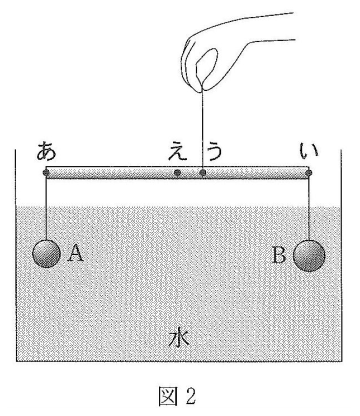
このあと、棒のかたむきはどうなりますか。正しいものを1つ選び、ア~ウの記号で答えなさい。
ア. あが上がる。
イ.いが上がる。
ウ. 棒は水平のままである。
(3)次に、棒を水平に保つように手で支えながら、おもりA、Bと棒をゆっくりと水そうの水の中に入れ、そっと手をはずし、図3の状態にしました。このあと、棒のかたむきはどうなりますか。(2)と同じ選択肢から、正しいものを1つ選び、ア~ウの記号で答えなさい。
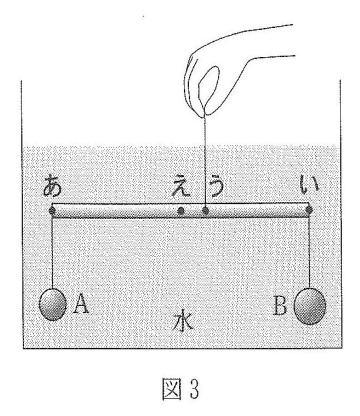
(4)(3)と同じ実験を、鉄の棒を太さがどこでも同じアルミニウムの棒(長さ30cm、重さ76g、体積28cm3)に変えて行いました。おもりA、Bとそれらをつり下げる位置あ、い、棒をつり下げる位置うは図3と同じです。すると、図4のように、棒の中心の点えに軽くて細いひもで、ある重さの鉄のおもりCをつり下げたとき、棒を水中で水平に静止させることができました。おもりCの重さは、何gですか。
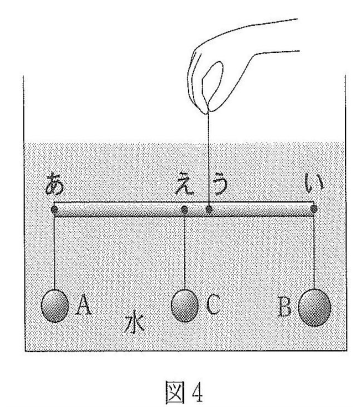
【解説と解答】
(1)
1)あからうまでの長さは18cm、うからいまでの長さは12cmです。
棒の重さを【1】とすると
55×18+【1】×3=110×12
990+【3】=1320 【3】=330より【1】=110g
(答え)110g
2)110+55+110=275g
(答え)275g
3)棒は鉄のおもりBと同じ重さですから、体積は14cm3になります。
(答え)14cm3
(2)Aの重さは55-7=48g Bの重さは110-14=96g
48×18+110×3=1194
96×12=1152よりいが上がります。
(答え)イ
(3)今度は棒にも浮力がかかるので、
48×18+96×3=864+288=1152で同じになります。
(答え)ウ
(4)棒の重さは76-28=48gになります。
Cの重さを【1】とすると
48×18+【1】×3+48×3=1152より
【3】=144
【1】=48
で、この鉄は1cm3あたり$$\frac{55}{7}$$gですが、水の中では$$\frac{48}{7}$$gになるので、
48÷48×55=55gになります。
(答え)55g
===========================================================
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
算数の復習はできなかった問題をやり直すこと
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
2月21日の問題
==============================================================
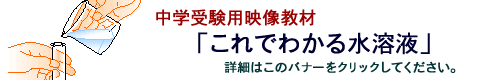
==============================================================
==============================================================

==============================================================
![]()
にほんブログ村