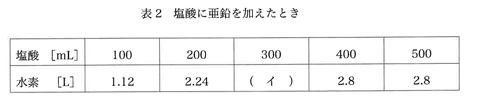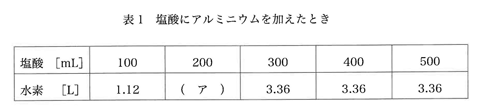2018年早稲田実業の問題です。
「各校の入試問題から」カテゴリーアーカイブ
気体に関する問題
2018年聖光学院の問題です。
次の文章を読んで,あとの(1)~(7)の問いに答えなさい。
1950年代,ヨーロッパの森の木が次々に枯れてしまったり,①ブロンズ像がぼろぼろになってしまったりする現象が起こりました。この現象の原因は後に,酸性を示す雨であることがわかりました。現在もなお,大きな社会間題とされています。
②雨はもともと弱い酸性を示していますが,ある量以上の酸が溶け込んだ雨を酸性雨とよびます。
酸性雨の原因は,③工場や自動車から出る排ガスなどにあることがわかっています。これらの排ガスが雨の中の水分と反応することによって,硫酸や硝酸などの非常に強い酸となって地表に降り注ぎ,さまざまな彰響を及ぼしています。酸性雨の原因となる排ガスは,空気に乗って瞬く間に拡がってしまうので,世界的な対策が必要不可欠です。現在では,これらの排ガスをなるべく出さないように色々な方法が考えられています。しかし,④ガソリンや軽油を使う自動車から酸性雨の原因となる排ガスを取り除くことは非常に困難な状況にあります。
そこで,ガソリンや軽油を使わず,酸性雨の原因となる排ガスをいっさい出さない自動車が開発されています。そのような自動車には,⑤燃料電池の一種である,水素が燃焼する際のエネルギーを取り出す電池や,リチウムイオン電池とよばれる充電可能な電池などが使われています。これらの電池を使っている自動車は,今までのガソリンや軽油を使う自動車と比較して,環境にほとんど負荷をかけずに済むようになりました。
(1)下線部①について,ブロンズは銅と何の合金ですか。最も適したものを,次の(ア)~(オ)の中から1つ選び,記号で答えなさい。
(ア)鉛 (イ) 銀 (ウ) アルミニウム
(エ)スズ (オ) 鉄
(2) 下線部②について,水は中性であるにもかかわらず,酸性雨の原因となる物質がいっさい空気中に存在していなくても,雨は弱い酸性を示します。その理由を簡単に答えなさい。
(3)下線部③について,酸性雨の原因となる物質の発生源は,工場や自動車などの人為的なもの以外にも存在します。人為的なもの以外の発生源として考えられるものを簡単に答えなさい。
(4)下線部④について,ガソリンや軽油を使う自動車では,エンジン内でガソリンや軽油を一緒に取り込んだ空気で燃焼させるため,どうしてもNOx(ノックス)とよばれも酸性雨の原因となる気体が排ガスに含まれてしまいます。NOxにあてはまる気体を,次の(ア)~(オ)の中から1つ選び,記号で答えなさい。
(ア)一酸化炭素
(イ)二酸化硫黄
(ウ)二酸化塩素
(エ)二酸化炭素
(オ)二酸化窒素
(5) 下線部⑤について,水素を燃料とする燃料電池自動車は,酸性雨の原因となる物質を排出しません。この燃料電池の反応によって排出される物質の名前を答えなさい。
(6) 水素の説明として正しいものを,次の(ア)~(キ)の中からすべて選び,記号で答えなさい。
(ア) 物質を燃やすはたらきがあり,水素が無いと物質は燃焼することができない。
(イ) 石灰水を白く濁らせるはたらきがあり,動物の吐く息に含まれている。
(ウ) すべての気体の中で最も軽い気体であり,かつて飛行船に使われていた。
(エ) 猛毒であり,毎年冬になると,中毒患者がでる事故が起こる。
(オ) 無色・無臭の気体であり,水に溶けにくい。
(カ) すべての気体の中で2番目に軽い気体であり,現在でも風船に使われている。
(キ) 地球の大気中で3番目に多い気体であり,電球の封入ガスとして使われている。
7)水素は,アルミニウムや壷路などの金属に塩酸を加えると発生します。
100,200,300,400,500mLの塩酸に,同じ重さのアルミニウムをそれぞれ加えたときに発生する水素の体積は表1のようになりました。
100,200,300,400,500mLの塩酸に,同じ重さの亜鉛をそれぞれ加えたときに発生する水素の体積は表2のようになりました。
表の中の(ア)・(イ)にあてはまる数値を答えなさい。ただし,使った塩酸はすべて同じ濃さであるものとします。
【解説と解答】
(1)ブロンズは銅とスズの合金です。
(答え)エ
(2)酸性雨の原因は二酸化炭素が溶けるから。
(答え)大気中の二酸化炭素がとけるから。
(3)火山の噴火によって酸化物が溶け込むことがありえます。
(答え)火山のふん火
(4)窒素酸化物ですから二酸化窒素。
(答え)オ
(5)水素を酸素が化合すると水になります。
(答え)水
(6)水素は最も軽く、水に溶けにくい性質を持っています。
(答え)ウ,オ
(7)アは1.12×2=2.24 イは1.12×3=3.36ですが400が2.8になっているので、2.8
(答え)ア2.24 イ2.8
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
もう塾に行くの?
5年生の教室から
パソコンの扱いが上手だと
慶應進学特別から
外国語作文の緩和
酸化に関する問題
2018年浦和明の星の問題です。
ものが燃えるとは,ものが空気中の「ある気体」と結びつくことです。金属も粉末にすると,空気中で燃やすことができます。燃やした後のものは燃やす前のものとは違うものになります。今,班ごとに金属Aと金属Bの2種類の粉末を用いて,燃やす前と燃やした後で,どのように重さが変化するかを調べる実験を行いました。ただし,実験に使用したステンレス皿の重さは34.0gで,熱することで変化しないものとします。次の各問いに答えなさい。
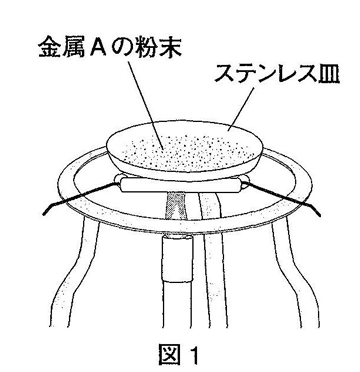
〔実験1〕
1)金属Aの粉末をステンレス皿にうすく広げ,皿全体の重さを測定した。
2)粉末を金属さじでかき混ぜながら,ステンレス皿の下からガスバーナーで加熱して燃やした(図1)。
3)粉末全体の色が変わったところで加熱をやめ,皿が十分に冷めてから皿全体の重さを測定した。
4)皿全体の重さが変わらなくなるまで,2),3)をくり返した。

〔実験2〕
1) 実験1と同じように,金属Bの粉末をステンレス皿にうすく広げ,皿全体の重さを測定した。
2) 粉末を金属さじでかき混ぜながら,ステンレス皿の下からガスバーナーで加熱して燃やした。
3) 粉末全体の色が変わったところで加熱をやめ,皿が十分に冷めてから皿全体の重さを測定した。
4) 皿全体の重さが変わらなくなるまで,2),3)をくり返した。
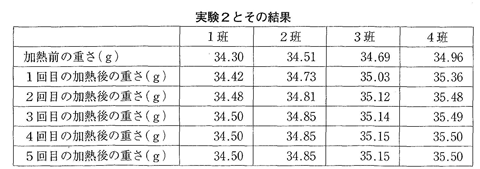
問1実験1について,次のa,bに答えなさい。
(a)金属Aの粉末と「ある気体」が結びつくとき,金属Aの粉末の重さと「ある気体」の重さの比はどのようになりますか。もっとも簡単な整数比で答えなさい。
(b)金属Aの粉末を完全に燃やしたもの4.5gにふくまれる「ある気体」の重さは何gですか。
問2 実験2について,5回目の加熱後であっても加熱が不十分であったと考えられるのはどの班ですか。また,このとき燃えずに残った金属Bの粉末の重さは何gですか。
問3 ある重さの金属Aの粉末と金属Bの粉末を,それぞれ重さが変わらなくなるまで加熱して燃やしました。すると,どちらの粉末も同じだけ重さが増えました。このときの金属Aの粉末の重さと金属Bの粉末の重さの比はどのようになりますか。もっとも簡単な整数比で答えなさい。
次に,金属Aの粉末と金属Bの粉末を混ぜ合わせたものを用意して,実験を行いました。
〔実験3〕
1) 金属Aの粉末と金属Bの粉末を混ぜ合わせたものをステンレス皿にうすく広げ,皿全体の重さを測定した。
2) 粉末を金属さじでかき混ぜながら,ステンレス皿の下からガスバーナーで加熱して燃やした。
3) 粉末全体の色が変わったところで加熱をやめ,皿が十分に冷めてから皿全体の重さを測定した。
4) 皿全体の重さが変わらなくなるまで,②,③をくり返した。
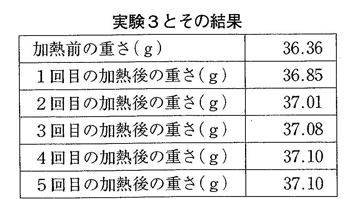
問4 実験3について,混ぜ合わせたものにふくまれる金属Bの粉末の重さは何gですか。
[解説と解答]
問1
(a)ステンレス皿は34gなので、1班はA0.48gに酸素が0.12g、2班はA0.64gに酸素が0.16g 3班はA0.92gに酸素が0.23g 4班はA1.16gに対して酸素0.29gになるので、4:1
(答え)4:1
(b)全体の5分の1になるので、4.5÷5=0.9g
問2
実験2では1班が3:2 2班も3:2 3班は0.69;0.46で3:2に、4班は0.96:0.54は3:2になっていないので4班。
0.54÷2×3=0.81 0.96-0.81=0.15
(答え)4班 0.15g
問3
Aは4:5 Bは3:5になるので、酸素の量が同じだとすればAが8:10、Bが3:5になるから、A:B=8:3
(答え)8:3
問4 A+B=2.36g $$\frac{5}{4}$$×A+$$\frac{5}{3}$$×B=3.1
$$\frac{5}{4}$$×A+$$\frac{5}{4}$$×B=2.95
$$\frac{5}{12}$$×B=0.15よりB=0.36g
(答え)0.36g
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
同じ学校を3回受けた子
5年生の教室から
海外から受験する
慶應進学特別から
湘南の憂鬱