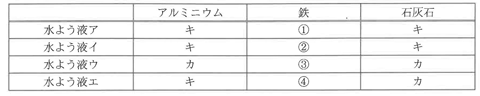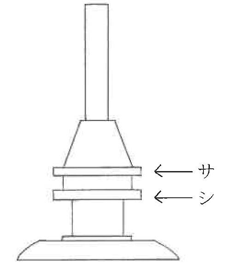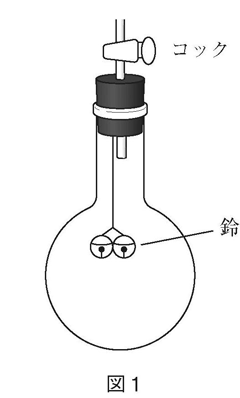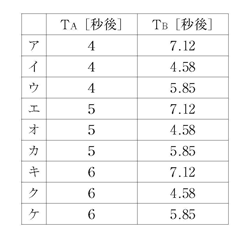2018年豊島岡の問題です。
次の文章を読んで,以下の問いに答えなさい。ただし.数値を答える場合は四捨五入して整数で答えること。
氷を加熱していくと液体の水に変わります。逆に液体の水を冷やしていくとやはり氷に変わります。
また,液体のアルコールを冷やしていくと,水と同様に固体になりますが,固体になる温度は異なります。
液体のときと固体のときの体積はそれぞれ温度により変化せず,液体から固体または固体から液体への変化にともない体積が変化するものとします。
さらに,液体の水1cm3の重さは1g,液体のアルコール1cm3の重さは0.9gです。固体になると水は10%体積が増え,アルコールは20%体積が減るものとします。
(1)100gの氷の体積は何cm3ですか。
(2)100cm3の液体の水に100gの固体のアルコールを入れると全体の体積は何cm3になりますか。ただし,水は液体のまま,アルコールは固体のままであるとし,完全にアルコールの固体は液体の水の中にあるものとする。
(3)100cm3の液体の水に100cm3の固体のアルコールを入れると,液体の水と固体のアルコールを合わせた重さは何gになりますか。
(4)100cm3の液体の水に(3)と同じ重さの液体のアルコールを入れると,この液体全体の1cm3あたりの重さは0.98gでした。このとき,液体全体の体積は何cm3ですか。
(5)液体の水と液体のアルコールが合わせて200gあります。これを別々にこおらせた後の体積の合計は液体のときと変わりませんでした。液体の水の体積は何cm3ですか。
【解説と解答】
(1)重さが変わらないので、100gですから水の時は100cm3なので、110cm3になります。
(答え)110cm3
(2)水は100cm3で、アルコールは100÷0.9×0.8=88.88≒89cm3なので、合計189cm3になります。
(答え)189cm3
(3)100cm3の水は100g。100cm3のアルコールは固体では125cm3になるので、0.9×125=112.5g≒113g
合計100+113=213g
(答え)213g
(4)113gのアルコールと水100gを混ぜると213gになり、この比重が0.98gになるから、体積は213÷0.98=217.3cm3≒217cm3
(答え)217cm3
(5)
液体の水の重さを(1)、アルコールの重さを【1】とすると、(1)+【1】=200g 液体のときの体積は(1)+【1】÷0.9となり、固体の時の体積は(1.1)+【1】÷0.9×0.8だから
(1)+【$$\frac{10}{9}$$】=(1.1)+ 【$$\frac{8}{9}$$】から200÷$$\frac{29}{9}$$≒62 水は200-62=138
(答え)138cm3
フリーダム進学教室 新連載 学校訪問シリーズ
第2回 東京都市大等々力中学
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
2019年入試変更情報-1-
5年生の教室から
自分で勉強することへの習慣化
慶應進学特別から
慶應湘南 学則定員変更 認可