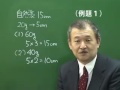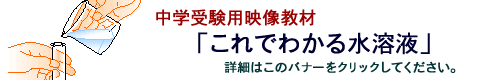2013年青陵中学の問題です。
図1のような形をした軽い棒のA点にひもをつなぎ、もう一方を天井に固定します。
 図1
図1
問1 棒の左端のB点に50gのおもりをつるしました。図1の状態でつりあわせるのは棒の右側のC点に何gのおもりをつるせばよいですか。ただし、棒の重さは無視できるものとします。
次に棒に重さがある場合について考えます。長さ30cm、1cmあたりの重さが10gの太さが均一な金属の棒BCを図2のようにBから20㎝のところで折り曲げます。
棒が同じ材質で、均一な太さでできている場合、棒の重さは棒の中央にまとまっていると考えることができ、この点を重心といいます。
 図2
図2
問2 次の文の( )にあてはまる数字を答えなさい。
この金属棒を、棒ABの部分と棒ACの部分に分けて考えます。
棒ABの重心はAから( 1 )cmの距離の点にあり、棒AB部分の重さは( 2 )gです。また棒ACの重心はAから( 3 )cmの距離の点にあり、棒ACの部分の重さは( 4 )gです。
問3 図2の上体で棒を静かにはなすと、棒はA点を中心にどちらの向きに回転を始めますか。次のア、イの文から正しいものを選び、記号で答えなさい。また、この図2の状態で静止させるには、図のB、Cのどちらに何gのおもりをつるせばよいですか。
ア 時計回りに回転を始める イ 反時計回りに回転を始める
問4 次に太さが均一な金属棒を図3のように折り曲げ、D点に糸を付けてつるします。このとき、棒はどのような状態で釣り合いますか。正しいものを次のア~オから選びなさい。
 図3
図3

(解説と解答)
問1
おもりの位置は水平で考えます。
 図4
図4
三角形PABは正三角形の半分の直角三角形ですから、PAの長さは20÷2=10㎝
したがって、Bに50gのおもりをつるせば、Cには50×10÷20=25gのおもりをつるせばつりあいます。
(答え)25g
問2 ABの重心はABの真ん中になるので、Aからは20÷2=10cmになります。ABの重さは10×20=200g
ACの重心はAから10÷2=5cm ACの重さは10×10=100gです。
(答え)(1) 10 (2)200 (3) 5 (4)100
問3
ABの重心は図4のAPの半分の距離ですからAから5cmのところにあります。
左側の回転力は5×200=1000 右側の回転力は5×100=500 したがって左側の回転力が勝るので、反時計回りに回ります。
静止するためには500の回転力を右側に足せばよいので500÷10=50g、Cにかければ良いことになります。
(答え)イ Cに50g
問4
20cmの部分の重さと10cmの重さの比は2:1 したがって左側の重心から糸までの水平距離と、右側の重心から糸までの水平距離の比は1:2にならなければなりません。そうなっているのは、エです。
(答え)エ
=============================================================
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
第一志望にこだわる
==============================================================
学受験 算数オンライン塾
11月16日の問題
==============================================================
お知らせ
算数5年後期13回 算数オンライン塾「仕事算」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================
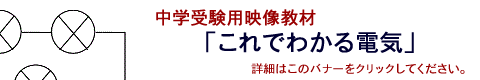
==============================================================

==============================================================
![]()
にほんブログ村