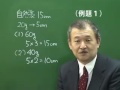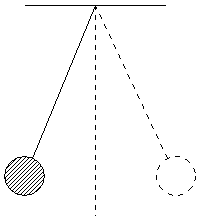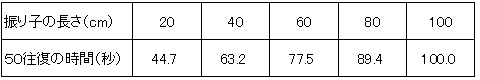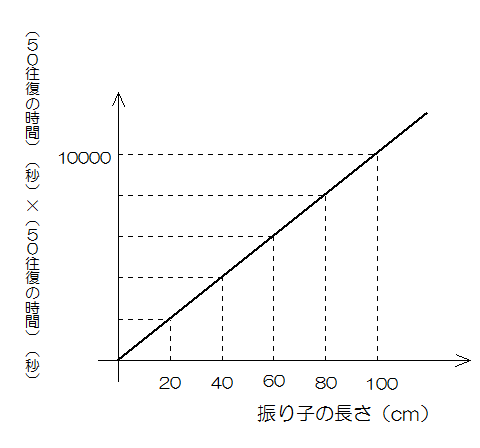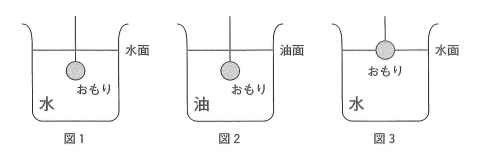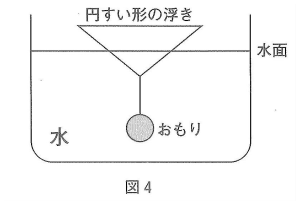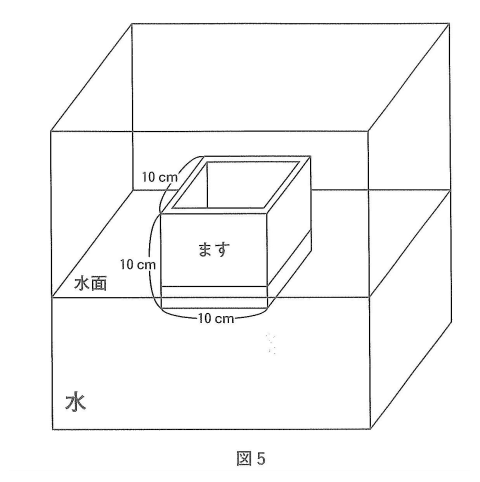2014年法政二中の問題です。
同じばねを何本か用意し実験を行いました。ただし、ばね、棒、糸の質量(重さ)は無視できるものとします。以下の問に答えなさい。
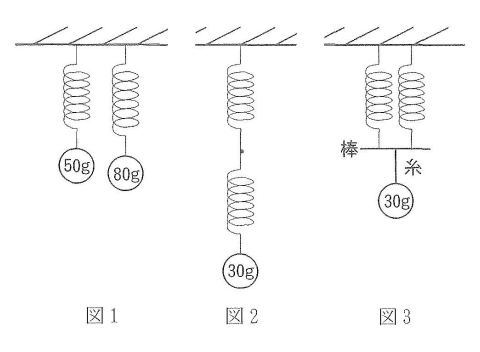
問1 図1のようにばねに重さ50gと80gのおもりをそれぞれつるしました。ばね全体の長さはそれぞれ15.5cm、17.3cmとなりました。
A このばねにおもりをつけていないときのばねの長さは何cmか答えなさい。
B このばねを1.0cm伸ばすのに必要なおもりは何gか、小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。
問2 図2のようにばねをたてにつなぎました。30gのおもりをつるしたとき、おもりが下がる長さは何cmか答えなさい。
問3 図3のようにばねを並べてつなぎました。30gのおもりをつるしたとき、おもりが下がる長さは何cmか答えなさい。
問4 図4は、一方を壁に取り付けてもう一方におもりをつるした様子を、図5は、ばねの両はしに同じおもりをつるした様子を示しています。このとき、図5のばねの伸びは図4のばねの伸びの何倍になるか答えなさい。ただし、ばねは伸びても定滑車には接触しないものとします。
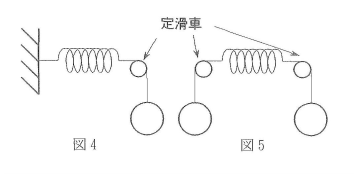
【解説と解答】
問1
A 30gの差が17.3-15.5=1.8cmですから、10gあたり0.6cmのびます。
したがって15.5-0.6×5=12.5cm
(答え)12.5cm
B 10gあたり0.6cmですから1cmは10÷0.6≒17g
(答え)17g
問2
ばねが直列ですから、ともに30g分伸びます。0.6×3×2=3.6cm
(答え)3.6cm
問3
並列の場合は重さが半分になるので、0.6×3÷2=0.9cm
(答え)0.9cm
問4
図4と図5は同じ状態です。壁が左側のおもりの代わりをしているだけです。
(答え)1倍
=============================================================
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
入試は模擬試験ほど忙しくはない
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
義塾創立の頃
==============================================================
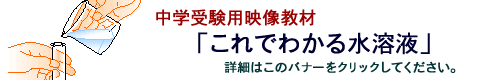
==============================================================
==============================================================

==============================================================
![]()