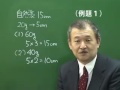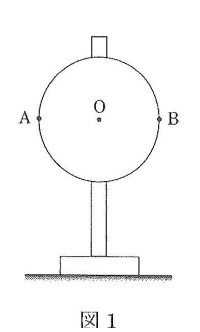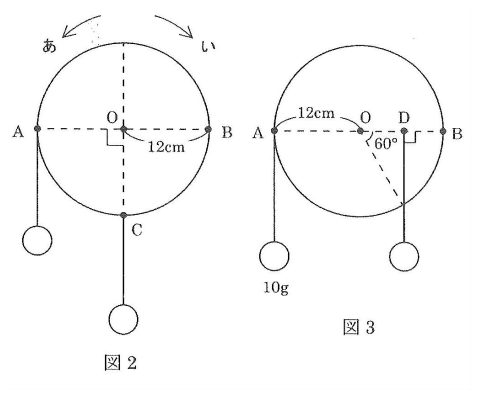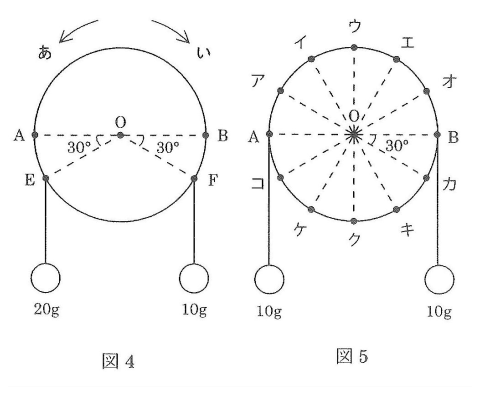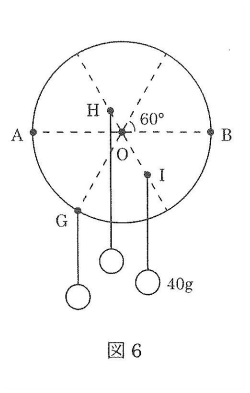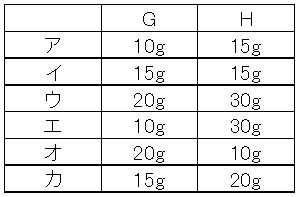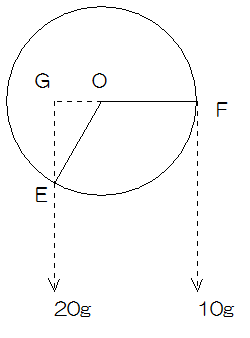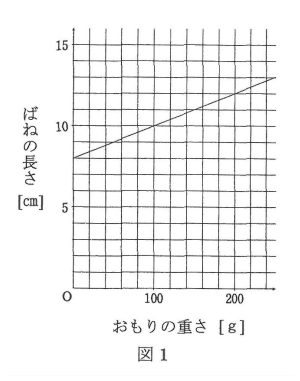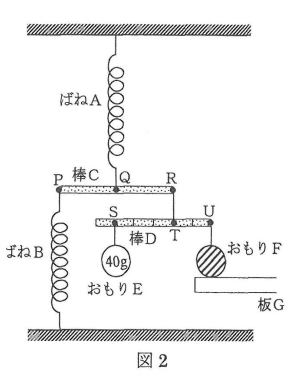2015年吉祥女子中学の問題です。
力のつりあいについて、後の問いに答えなさい。ただし、ばねや糸の重さは考えなくてよいものとします。
図 1 はばね1とばね2について、つるした物体の重さとばねののびの関係を示したものです。ばね1、ばね2、重さが100gのおもりA、重さが50gのおもりBを図2、図3のように接続し、天井からつり下げたところ、どちらの場合もすべてのおもりは静止しました。
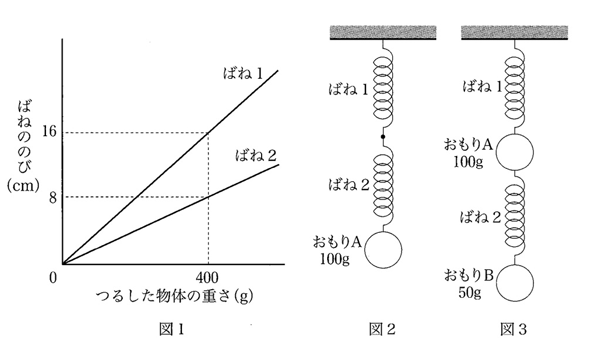
(1) 図2において、ばね1ののびとばね2ののびはそれぞれ何cmですか。
(2) 図3において、ばね1ののびとばね2ののびはそれぞれ何cmですか。
次に、重さのわからないおもりCと、ばね2と同じ性質を持つばね3と定滑車を、新たに用意しました。図4のように、おもり A, B, Cとばね1, 2を接続したところすべてのおもりは静止しました。また、図 5のようにおもり A, B, Cとばね 1, 2, 3 を接続したところ、すべてのおもりは静止しました。
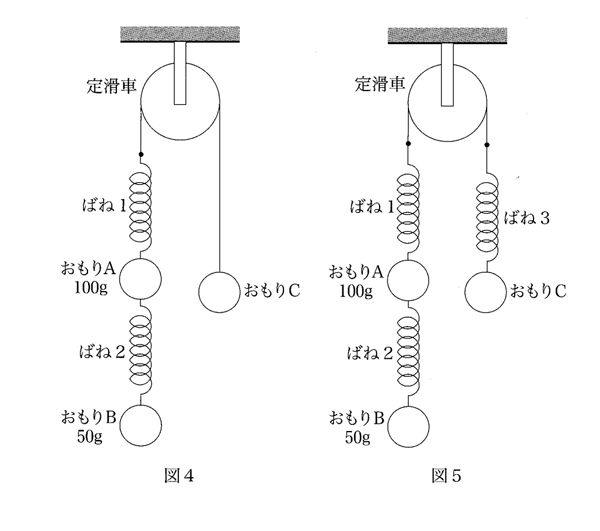
(3) 図4において、おもりCの重さは何gですか。
(4) 図5において、ばね3ののびは何cmですか。
次に、重さが100gで、中に水を入れることのできる容器P,Qを用意しました。中に水を入れない状態で、ばねIとばね2を用いて図6のように接続したところ、2つの容器は静止しました。このときの容器Qの下面の深からの高さを測定したところ30cmでした。
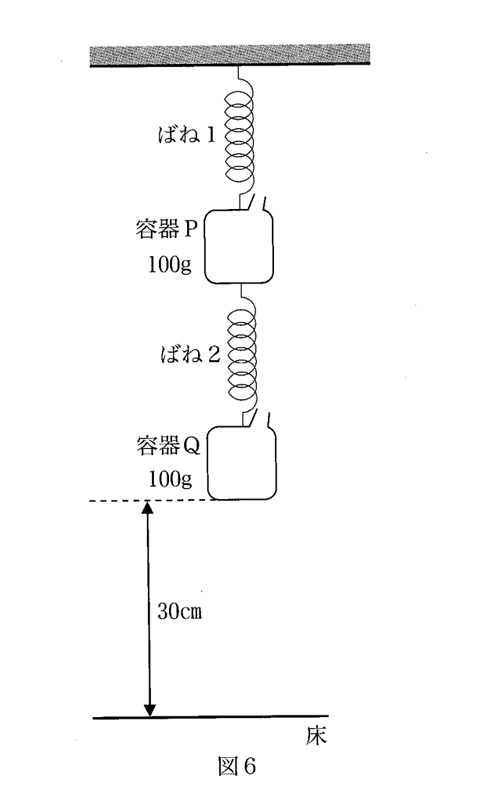
(5) 図6の状態で容器Pに50gの水を入れると、容器Qの下面の床からの高さは何cmになりますか。
(6) (5)で入れた水を長いて図6の状態に戻した後、容器Qにある量の水を入れると、容器Qの下面の床からの高さは25.5cmになりました。容器Qに入れた水は何gですか。
次に、つるした物体の重さとばねののびの関係が図7のようになるばね4を用意しました。2つの容器に水を入れない状態で、図6の状態からばねlをばね4に取りかえたところ、2つの容器は図8のように静止しました。このときの容器Qの下面の床からの高さを測定したところ20cmでした。
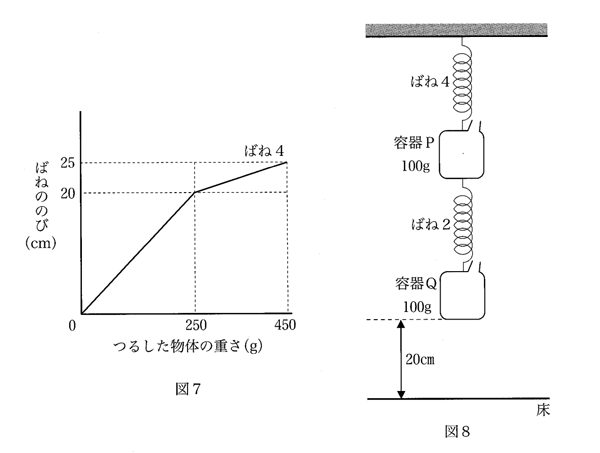
(7) 図8の状態で容器Pに150gの水を入れると、容器Qの下面の床からの高さは何cmになりますか。
(8)(7)で入れた水を抜いて図8の状態に戻した後、容器Qに70gの水を入れると、容器Qの下面の床からの高さは何cmになりますか。
【解説と解答】
(1)
図2では100gの重さは両方のばねにかかります。
ばね1は400gで16cm伸びますから、100gでは4cmです。ばね2は400gで8cmですから、100gでは2cmです。
(答え)ばね1 4cm ばね2 2cm
(2)
図3ではばね1には150g、ばね2には50の重さがかかります。
ばね1は150gですから6cm、ばね2は1cmになります。
(答え)ばね1 6cm ばね2 1cm
(3)
ばねの重さがないので、おもりCの重さは150gです。
(答え)150g
(4)
ばね3はばね2と同じ性質を持つので、100gで2cm伸びます。
150gとわかりましたから、3cmのびます。
(答え)3cm
(5)
容器Pだけに水を入れると、ばね1が伸びますから、全体がばね1が伸びる分だけ下がります。
50g入れるとばね1は2cm伸びるので、30−2=28cmです。
(答え)28cm
(6)
容器Qに水を入れると、ばね1、ばね2が伸びます。
100g入ると、ばね1は4cm、ばね2は2cmのびるので合計6cm伸びます。
4.5cm伸びていますから、4分の3になるので75g入れたことになります。
(答え)75g
(7)
水を入れない状態でばね4には200gかかっています。これに150g加えると、350gかかりますから、ばねののびが変わります。
200gから250gになるところまでは、50g増えるので4cmのび、その後は200gで5cmですから、100gでは2.5cmのびるので20−2.5−4=13.5cmになります。
(答え)13.5cm
(8)
容器Qに70g入れるとばね4には270gかかるので、ばね4ののびは4+0.5=4.5cmになります。
さらにばね2は1.4cmのびるので合計5.9cm伸びますから、20−5.9=14.1cmになります。
(答え)14.1cm
==============================================================
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
我が家はどうするか
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
教室に入ったら
==============================================================
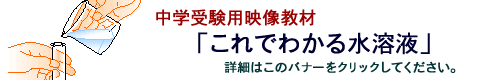
==============================================================

==============================================================

==============================================================
![]()
にほんブログ村