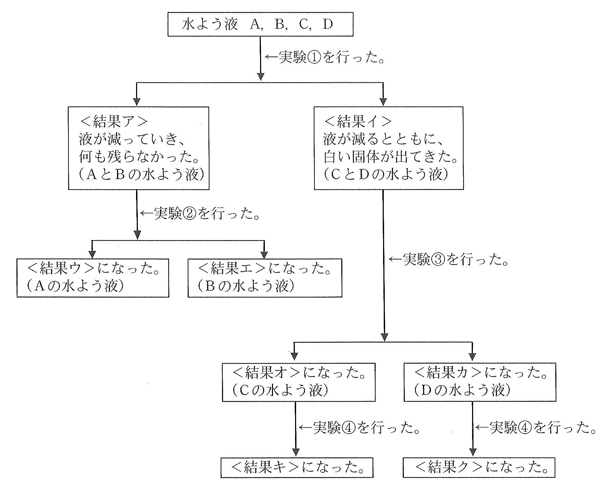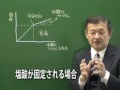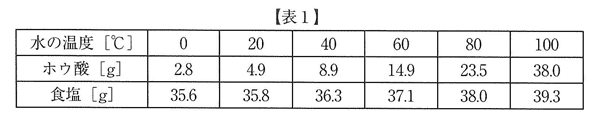夏期講習が始まって、たくさんの勉強をしていますから、当然、授業中にわかることばかりではないでしょう。
となると、ある程度復習をしないといけないし、また勉強したことを実際に自分で使いこなせるようになるために問題演習をしないといけないでしょう。
こういう時間は、少なくとも講習に行っている限りは最も優先しなければならない勉強です。
というのは、それだけ講習に時間をかけているからで、その時間を無駄にしないためにもまず、この復習と宿題にエネルギーを注いでいいでしょう。
ただ、できることを繰り返す、というのはある意味無駄だとも言えます。ところが子どもたちは、やらなきゃいけないこととして、やっているわけだから、そこはある程度親の方でコントロールしなければならないのです。
本来しっかり復習をしっかりやるべきではあるものの、もう充分にできるよね、と思われるのであれば、それは飛ばしていいのです。
このメリハリがないと時間を有効に使えません。
ですから、常に「できるようになっているか」という点を見据えながら、上手に勉強の時間をコントロールしてあげてください。
============================================================
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
9月以降の学校別対策
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
中和に関する問題
==============================================================
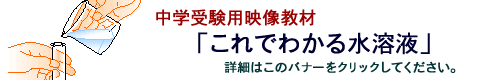
==============================================================

==============================================================

==============================================================
![]()
にほんブログ村