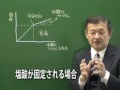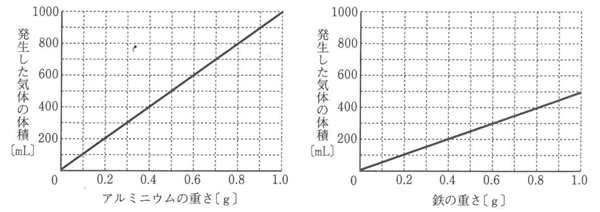2016年市川学園の問題です。
市川君はお風呂に発砲入浴剤を入れたときに気体が発生することを不思議に思い、夏休みの自由研究として調べることにしました。
その結果、入浴剤に含まれる薬品が水の中で混ざることで気体が発生すること、薬局で売っているクエン酸と重そうから発泡入浴剤を手作りできることがわかったので.実験してみることにしました。
まず、100gの水に4.00gのクエン酸を溶かした水溶液をいくつか用意しました。そして、それぞれの水溶液に異なる重さの重そうを加え、気体が発生し終わってから十分に時間がたった後の水溶液の重さをはかりました。
その結果を表1にまとめました。
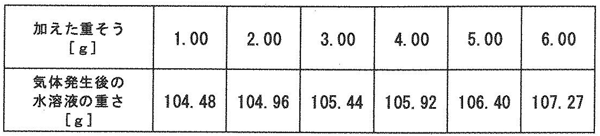
表1
(1)下線部の気体は何ですか。
(2)この実験で、重そうを2.75g加えると気体は何g発生しますか。
次に、この実験の結果から考えて、最も多く気体が発生する割合でクエン酸と重そうを混ぜ合わせて発泡入浴剤を作りました。
(3)作った発泡入浴剤10gには重そうが何g含まれていますか。
(4)作った発泡入浴剤20gに十分な量の水を加えると気体は何g発生しま
すか。
(1)重そうとクエン酸ですから、二酸化炭素です。
(答え)二酸化炭素
(2)重そう1.00gのとき、100gと4gと1gで合計105gですか、発生後は104.48gですから、0.52g二酸化炭素が発生します。
重そう2.75gの場合は0.52×2.75=1.43gです。
(答え)1.43
(3)表1からそれぞれ発生した気体の重さは、
(重そうの重さ、気体の重さ)=(1.00,0.52)(2.00,1.04)(3.00,1.56)(4.00,2.08)(5.00,2.6)(6.00,2.73)
となり、6.00g のとき、0.52g×6=3.12gまで出ていないことから、5gと6gの間で終わっていることが分かります。
2.73÷0.52=5.25gより、このクエン酸4.00gに対して重そう5.25gを加えると二酸化炭素が最大になることから、
4:5.25=16:21 したがって10÷37×21=5.675≒5.7g
(答え)5.75g
(4)クエン酸4.00gに対して重そう5.25gを加えると二酸化炭素は2.73g発生します。
20gに含まれるクエン酸の量は20÷37×16=8.64gなので、8.64÷4.00=2.16より2.73×2.16=5.90g
(答え)5.90g
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
雪の対策は防寒とくつ
5年生の教室から
4年生のうちにやってほしいこと
今日の慶應義塾進学情報
体育実技で大事なポイント