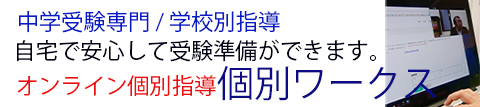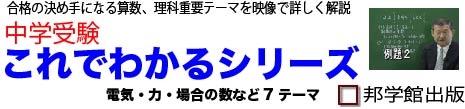今の中学受験の加熱化はやはり子どもたちの負担を一気に増やしているところがあります。
2年生からの通塾もそうですが、途中、多くの組み分けや月例テストは、確かに勉強の進捗をはかる上で必要ではあるものの、進捗をはかることよりも順位やクラスばかりに目が行っていて、子どもたちはそればかりを指摘されているような感じ。
それが3年も続けば、誰だっていやになる感じがします。
だから、まあ、適当に距離を置いた方が良いのです。
さすがに6年生はいろいろがんばった方が良い、と思いますが、それまでの間は、どちらかを言えば基礎を中心にして、本人ができることを確実に積み重ねていくことの方が大事。
あまりにたくさんの課題を与えられて、いやになっている受験生は少なくないのです。
でもそんなことをしないと合格しないのか?といえばそうではありません。
塾は営利団体ですから、儲けなければいけない。だから、当然、必要だといいますが、必要でないことは見ていてたくさんある。
だからやはり本当に必要なことを見分ける目は持っていた方が良いと思うのです。
例えばうまくいっていないなと思ったら、いったんその戦いから距離を置いても良いのです。クラスが下がっても別に良い。
それよりも子どもの心と体の健康をしっかり維持して、最後の1年間で伸ばそうという作戦に打って出た方が良いでしょう。
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事
志望校が決まれば勉強の内容も変わる
フリーダムオンライン-学習のヒント-
学習履歴データ化の目的
フリーダムオンライン-お知らせ-
夏期講習のお知らせ
【塾でのご利用について】
フリーダムオンライン WEBワークスOEMのご案内
読んでいただいてありがとうございます。
![]()
にほんブログ村