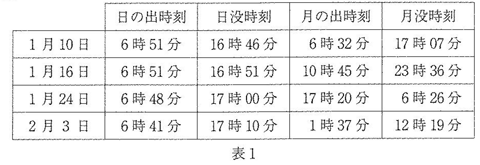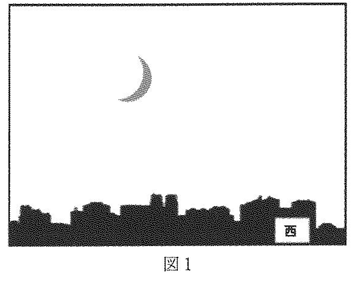算数の問題を出して、子どもたちが解いてくるのを採点していると、まあ、ちょこちょこ良く間違う。
「はい、やり直し」
というと、まあ、すぐに正解になってくることも多いのですが、しかし、入試ではこれが利かない。
だれも「はい、やり直し」とは言ってくれない。自分でそれを判断して、試験時間内に修正できなければいけないからです。
だからこれからはとにかく「正確に解きあげる」という練習をしていかないといけない。問題量もある程度必要だが、いい加減に解いてしまったのではあまり練習にはならない。
正確にきちんと解く、という練習を続けていきましょう。
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
塾に来たがる子
5年生の教室から
式を書く
今日の慶應義塾進学情報
分度器で測ってはいけない