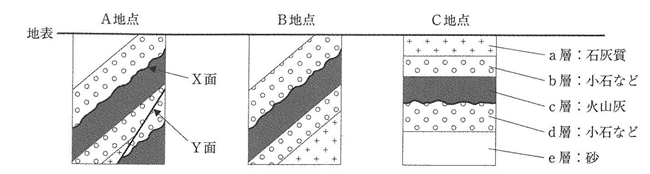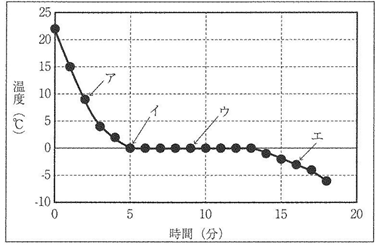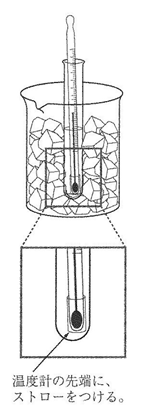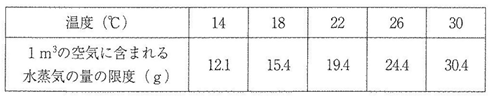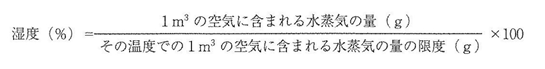2017年立教新座の問題です。
下の図はある地域のA~C地点の地層の様子をあらわしたもので、各地点で観察された火山灰の 層は、同じ時代にたい積したことがわかっています。この地層について、以下の問いに答えなさい。
(1) X面のような境界面を何といいますか。
(2) Y面のように地層がずれていることを何といいますか。
(3) Y面ができたときに、A地点の地層にはたらいた力の説明として適切なものを、次の(ア)~(エ)から選び、記号で答えなさい。
(ア) A地点付近を中心に外側に水平に引っ張る力
(イ) A地点付近を中心に内側に水平に押し合う力
(ウ) A地点付近を左側に水平に移動させようとする力
(エ) A地点付近を右側に水平に移動させようとする力
(4) ぎょうかい岩が見つかりやすい地層を、図のa~e層の中から選び、記号で答えなさい。
(5)石灰岩の元になった生物として適切なものを、次の(ア)~(オ)からすべて選び、記号で答えなさい。
(ア) フズリナ (イ) ケイソウ (ウ) サンゴ (エ) クラゲ (オ) テングサ
(6) A地点では小石などが含まれる地層が複数あり、それぞれの地層では下の方にいくほど小石の大きさは大きくなっていました。B地点 C地点の小石などが含まれる地層の特徴として適切なものを、次の(ア)~(エ)から選び、それぞれ記号で答えなさい。
(ア) それぞれの地層では、下の方にいくほど小石の大きさは大きくなっていく
(イ) それぞれの地層では、下の方にいくほど小石の大きさは小さくなっていく
(ウ) それぞれの地層では、上下に関係なく同じ大きさの小石がある
(エ) それぞれの地層では、上下に関係なく大小さまざまな小石がある
(7) 図のa~e層を、たい積した時代の古い順に並びかえなさい。
(8) この地域の地層が形成された過程について、もっとも古い時代に起きた現象を、次の(ア)~(ウ)から選び、記号で答えなさい。
(ア) Ⅹ面の形成 (イ) Y面の形成 (ウ) 地層のしゅう曲
【解説と解答】
(1)不整合面です。
(答え)不整合面
(2)断層です。
(答え)断層
(3)左側が上にかぶっているので、逆断層。
(答え)イ
(4)凝灰岩は火山灰が堆積した岩です。
(答え)c
(5)石灰岩はフズリナ、サンゴなどの死骸が固まったものです。
(答え)アウ
(6)不整合面のギザギザの向きがAとBは同じですから、Bは下の方に向かって大きくなり、Cは逆になります。
(答え)B地点 ア C地点 イ
(7)Cは逆転しているので、上から順に堆積したと考えられます。
(答え)a→b→c→d→e
(8)Xの不整合面がABCすべてに入っているので、この不整合面が一番古いことがわかります。
(答え)ア
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
プラスに考える道
5年生の教室から
自分で勉強する姿勢を身につけるために
今日の慶應義塾進学情報
受験番号は気にしない