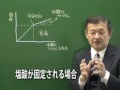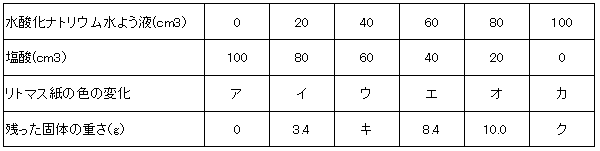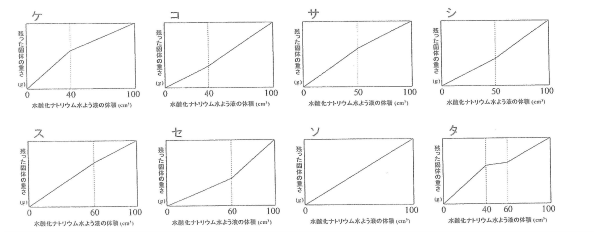2015年筑波大付属駒場の問題です。
無色の液体A~Dについて、次の実験1~4を行った。後の各問いに答えなさい。ただし、液体の1つは水、他の3つはそれぞれ異なる水よう液である。
【実験1】試験管に液体Aをとり、小さな金属板を加えたところあわが出た。その後、金属は小さくなりあわは出なくなった。
【実験2】試験管に液体Bをとり、塩のつぶを加えたところ細かなあわが出たが、つぶにはほとんど変化が見られなかった。その後、試験管をふってかき混ぜるとつぶは見えなくなった。
【実験3】試験管に液体Cをとり、塩のつぶを加えたところ、つぶにはほとんど変化が見られなかった。その後、試験管をふってかき混ぜるとつぶは見えなくなった。
【実験4】試験管にとった液体Dに、液体Bを加えたところ白いにごりができた。また液体Dは、呼気をふきこんでも白いにごりができた。
1.実験1~3において、実験後に残った液体をスライドガラスに取り、水を蒸発させたときの変化として最も適したものをそれぞれ答えなさい。
ア 液体に加えた金属がスライドガラス上に残る。
イ 液体に加えた塩がスライドガラス上に残る。
ウ 液体に加えた金属とはちがうものがスライドガラス上に残る。
エ 液体に加えた塩とはちがうものがスライドガラス上に残る。
オ 何も残らない。
2.液体A~Dをガラス棒でリトマス紙につけたときに予想される結果について、それぞれ答えなさい.
ア 青色リトマス紙が赤くなる。
イ 赤色リトマス紙が青くなる。
ウ 赤色リトマス紙も青色リトマス紙も変化しない。
エ 今回行った実験の結果だけではわからない。
3.次の身近な水よう液で、実験1と同じ操作を行ったとき、液体Aと同じような変化が観察されるものはどれですか。
ア.食塩水 イ 砂糖水 ウ せっけん水 エ す(食酢)
【解説と解答】
1 Aは塩酸のように、金属を溶かしたわけですから、溶けた金属と水溶液の一部が化合した金属が残ります。答えはウ。2、3は塩が溶けたので、蒸発させれば塩が残るからイ。4
(答え)1 ウ 2 イ 3 イ
2 A 金属を溶かすものは酸性にもアルカリ性にもあるので、エ。 Bはあわが出ているので塩酸のように酸性と考えられるのでア、 Cは水を思われるのでウ。 Dは石灰水と思われるのでイ。
(答え)A エ B ア C ウ D イ
3 金属を溶かすものとして考えられるのは酢酸です。
(答え)エ
「映像教材、これでわかる水溶液」(田中貴)
==========================================================
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
まずは解ければいい
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
女子はやはり難しいが・・・
==============================================================
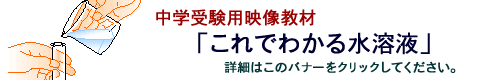
==============================================================
==============================================================

==============================================================
![]()
にほんブログ村