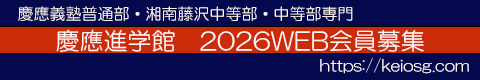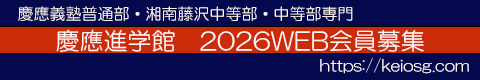すでに各塾では新年度の時間割やスケジュールが発表されていると思います。
1年前から通塾を始めた4年生は、この1年間、ずっと競争させられてきたわけですが、この生活があと2年間続きます。毎月のクラス昇降は、結構負担が大きかったのではないでしょうか。
本来、第一志望の違う子どもたちを同じ土俵で競争させる必要はありません。しかし、授業のレベルを合わせるために、という大義名分で行われている組み分けテストですが、子どもたちの実力とクラスが合わないことはいくらでもある。子どもたちの科目バランスが違うからです。細かいことをいえば、各教科で成績順に分けなければいけないが、まずそんな面倒なことはしない。だいたいは合計点数で組み分けをするわけだから、やはり競争させることで力をつけようとしている、のです。
しかし、もうこれははっきりしてきたことですが、その競争に勝てる子は少ないので、むしろ勝てない組が大きなロスを強いられる仕組みなのです。まだ小さいですから本人たちに自信がつかないだろうし、やる気も削がれてしまうところがある。
1年やっても大変だったのに、さらに2年続ける、というのは果たして本当に我が子にとって良いのか、もう一度考えるべき時期に来ています。
これは新6年生も同じです。
2年間の競争で、もう疲れ果てている、という子も少なくないでしょうし、それでロークラスにいるとやはりモチベーションが上がっていかない。最早そういう競争とは訣別して、第一志望校に合わせた対策を早めに始める方が力は伸びる可能性があるのではないでしょうか。
組み分け対策に翻弄される時間がもったいないのです。
間もなく入試休みに入るでしょうから、さらに消耗戦を続けるのか、もう一度考えてみるべきだと思います。