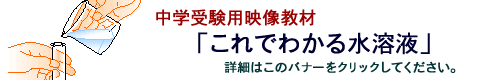割とこういう話を聞かされるのですが、塾に行こうが行くまいが、その子の勉強量が充分であれば、当然合格できるに決まっています。以前、ある中学受験の通信教育に関わったことがあります。その時は「塾に行かずとも合格できる」というフレーズがやはり出ておりました。本当はそんなことはどうでもいい。きちんと、子どもたちに勉強する教材を提供し、フォローし続けられれば、お父さん、お母さん、そして子どもたちも安心して勉強するし、結果もついてくるだろうと思います。
以前、アメリカの片田舎にお父さんの仕事の関係で転勤していた子どもが、突然、日本に帰ってくることになった。英語ができるのだから、まあ、高校受験でも良いとは思ったが、タイミングが間に合うので中学受験に挑戦したい、というお話で、メールのやりとりや、教材のお話をしつつ、受験してもらったところ、見事に合格しました。だから、まあ、どこにいても、どういう教材をやっても、しっかり勉強できて、入試問題が解ければ問題はない。
で、このお話をしようと思ったのは、実際に塾に通っていても「勉強していない」子が少なくない、からです。
塾に行っているから、勉強している、ということには実はならない。つまり、勉強している雰囲気ではあるし、授業には参加しているのだが、結局、勉強していない。習ったことがわかっていないし、また復習もできないから、そのままになる。(復習ができないのは、本人の意思とはまた別に時間がまったく不足するという場合も散見されるのですが。)その結果として、理解していないことが積み重なり、ほぼ塾では何をしているか、本人はわからなくなってしまっている。
これはやはり時間のムダだから、何かやり方を変えればいいのだが、もとより塾の方はやめさせる気はないし、お父さん、お母さんも「そのうち何とかなるのではないか」と思うのだが、まず何とかなりません。
塾に行かずに合格できるし、塾に行っても合格できない。本質は勉強ができているか、ということであって、どんなに良い教材を使ったところで、本人がわかっていないければ何のプラスにもなりはしないのです。これが中学生や高校生ならば、自分で「別な方法」を考えるかもしれない。しかし小学生自身は「方法を変える」ということはあまり思いつかないでしょう。「いやなこと」があれば、塾をやめたいというかもしれませんが、「この授業を聞いていても、僕はできるようにならないから、他の方法を考えてほしい」という子どもはまずいないのではないでしょうか。
だから、お父さん、お母さんが考えないといけないのです。ここが中学受験の難しいところです。塾は「お子さんのためにならないので、おやめください」とは言わないでしょう。「なんとかしましょう」というのです。熱心に教えてくれる先生も多いが、それでもうまくいかないとすれば、何かを変えてあげないと、結局はコストがムダ、ということになってしまいます。
今年の2月から、4か月が経過しました。ちょうど1年の3分の1。受験学年でいえば、あと3分の2で入試になります。
本当に今のやり方に納得されていますか。この機会にぜひ考えてみられると良いのではないでしょうか。
==============================================================
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
算数のノートの使い方、あれこれ
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
5月25日の問題
==============================================================