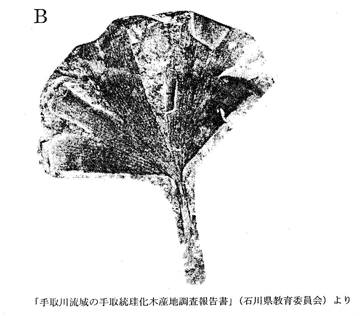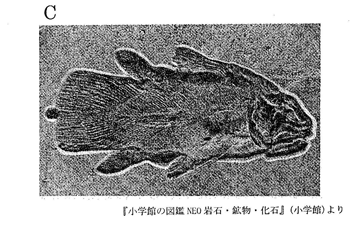「1週間にこなす問題はどのくらいが適当なのでしょうか?」という質問をよく受けます。実際には子どもによって違うので、これだけのことをやればいいということはありません。
例えば算数についてその週のテーマがひとつあるとしましょう。当然、そのテーマについてまず基本問題があって、それを応用した練習問題がテキストにはあるでしょう。ある生徒にとってはまず基本を学ぶことが大変であったとします。とすれば1週間で練習問題までたどりつくには相当大変でしょう。しかもその問題の理解は手を出すだけにとどまってしまう可能性が高いのではないでしょうか。
一方、ある生徒にとっては基本はすぐわかってしまって、例題、基本問題も簡単で練習問題までそこそこできてしまうかもしれません。
これが確かに力の差といえるかもしれません。ここで試験であれば、当然のことながら頭の良い子が有利になることは間違いないでしょう。しかし、入試は初学を競うのではありません。じっくり準備をしてできるようになったところで競争をするわけですから、単に頭のいい子ばかりが勝つ勝負ではないのです。
で、前者の子であれば、基本だけをまずしっかり学習すればいいのです。そしてそれが理解できたら、その次の機会に練習問題に進めばいいのです。最初のうちは、頭のいい子との差はどんどん広がっていくでしょう。しかし、範囲には限りがあります。やがて初学のものはなくなり何度か学習した範囲での勝負になってくるのです。そうすれば基本をじっくり身に付けた子が次第に差をつめていくでしょう。その結果として毎年、入試のころは定員の2倍程度の子どもたちの力の差はほとんどなくなっていくのです。
「今出来ないことを考えるより、今出来ることに集中する」ことが重要なのです。そしてひとつ理解できれば必ず理解は連鎖的に広がります。その過程でおもしろさもでてくるし、自信も生まれるものなのです。もちろん楽なことばかりを考えるのではありません。ある程度負荷がかからなければ力はつきませんが、だからといって到底不可能なことを追いかけても何も生まれないのです。
今がんばってできることに集中する、その結果としてできる問題数が子どもたちの「適正学習量」ということができるでしょう。
フリーダム進学教室 新連載 学校訪問シリーズ
第2回 東京都市大等々力中学
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
記述は書き慣れることが大事
6年生の教室から
学校別スタディールームオンライン
慶應進学特別から
慶應入試説明会を終えて
自宅でできるオンライン個別指導「スタディールームオンライン」