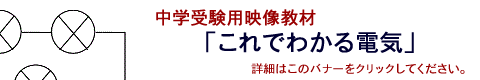問題ができなかったり、テストの点が悪かったりすれば、当然、子どもは落ち込みます。
しかし、ここで「どうせ、私、できないから。」と思ってしまうと、もうそれ以上の成長は期待できなくなる。
できなくてもいいから、何とかできるようになろう。あるいは、とにかくわかってやろう、というような意欲はとても大事なのです。
点数が悪かったから叱る、というのは決して子どもの教育にはプラスにならない。
勉強する態度が悪かったり、そもそも勉強していない、というのであれば叱る意味もあるが、本人が本人なりにがんばっているときは、口は慎むべきです。
そして、何とかわかってやろう、できるようになってやろう、という気持ちを支えてあげる必要があります。
できなくても、もう一度考える。あるいは解説を読んで納得する。
もう一度似たような問題をやってみる。
そういう過程を経て、できるようになれば良いのであって、もとになる意欲をそぐようなことを言ってはいけないのです。
ただ、そういう気持ちがあっても具体的に何をやっていいか、絞り込めていない場合もあるでしょう。
だから励まして、具体的に何をやるかを決めて、実行するのです。
それさえできれば、子どもの成長には必ずプラスになります。
できなかった、というときこそ、お父さん、お母さんが口角を上げるときなのです。
==============================================================
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
組み分けテストのわな
==============================================================
中学受験 算数オンライン塾
5月2日の問題
==============================================================

==============================================================
お知らせ
算数5年前期第15回 算数オンライン塾「まとめのテスト」をリリースしました。
詳しくはこちらから
==============================================================

==============================================================
![]()
にほんブログ村