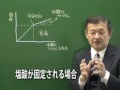入学式、始業式と始まり、新学年になりましたね。
春休みの生活から、また4か月間、いわゆる通常授業というか、学校と塾がある生活が始まります。
特に4月は学校でクラス替えがあったり、担任の先生が変わったりした子どももいるでしょう。まずは新しい生活環境に慣れる、ということが大事です。
また塾も夕方からになりますから、勉強時間を上手に計画していかなければなりません。
2月、3月に比べてこれから、また勉強は難しくなっていきます。
6年生は志望校を意識した内容も出てくるでしょう。したがって、しっかり復習をしたり、宿題をこなしたりしなければなりません。
そこで、もう一度1週間のスケジュールを立ててみましょう。
月曜日から始まってそれぞれの日にどんな勉強をすればいいのか。
勉強時間の話でもお話しましたが、毎日どのくらいの時間勉強するかを決め、それにあわせて具体的にどんな勉強をするか、絞り込んでいきましょう。
塾のスケジュールも決まっていますから、いつまでに何をしなければならないかもはっきりしているはずです。
それがすんだら次は、組み分けテストなり、マンスリーテストなりの日程に合わせてやらなければいけないことを考えます。
やはりテストに向けて暗記をしたり、復習をしたりということは必要なはずで、その勉強を加えるとすると、その週は週間のスケジュールが狂うはずです。
ですから、少なくとも2つの方向、週間と月間のスケジュールを考えてみる必要はあるのです。
まず新学期はここをもう一度再検討してみる必要があるでしょう。
2月、3月でも経験しているわけですが、新学年になるとやはり、問題をこなす量も増えてきますし、難度も上がってきます。だからもう一度、見直しをして具体的に何を勉強するか、決めていきましょう。
やることを決める、ということはやらないことを決める、ということでもあります。
「あれも、これも」
と思うことはありますが、時間は限られます。
やるべきことに優先順位をつけて、
「これだけはしっかりやりきる」
ようにしていくことが大切です。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
まとめのテストの意義
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
決断を強いる
==============================================================
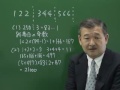 「映像教材、これでわかる数の問題」(田中貴) |
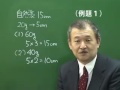 「映像教材、これでわかる力のつりあい」(田中貴) |
 「映像教材、これでわかる場合の数」(田中貴) |