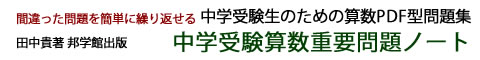算数で基本問題から出題する学校の対策として、一行問題の習得は非常に大事です。
では、それが出ない学校は不要か?
というと、そんなことはありません。
応用問題というのは、いくつかの論理過程が積み重なっています。そのひとつひとつはこういった一行問題で構成されていることが多い。
例えば、流水算の基本に
(下りの速さー上りの速さ)÷2=流れの速さ
というのがありますが、上りの時間が12分、下りの時間が8分とわかる問題であれば、下りの速さは【3】とおけ、上りの速さは【2】とおけるから、流れの速さは【0.5】とおくことができるようになるわけで、これは問題を解くときの道具に当然なるわけです。
したがって、夏休みまでに一通り、一行問題は習得できることが望ましい。これが私のいう、算数の基礎です。基礎を固める、というのはすべての分野の基本問題ができることであって、あとはそれをどう組み合わせるかは、応用問題を解きながら論理の組み立て方を勉強するようにしていけばいい。
ただ、基礎をすっ飛ばしてしまうと、これがうまくいかない。
道具がないから、論理が組み立てられなくなるのです。
ひとまず全範囲の授業が終わったら、まずは一行問題の習得に力を入れることでしょう。一通りできる、ということになるまでは、あまり他のことはやらなくていい。夏休みの前半は、その習得に力を入れていく。それである程度自信がついたら、次は過去問へ、という流れが良いと思います。
一行問題は、やさしい、と思いがちですが、良く問題を読まないとひっかかることがある。ミスが出やすい。これは本人が「あ、これ知ってる」とか「これ、できる」と思ってしまうからです。しかし、少し問題が変えてあったりして、ひっかかる。ミスの対処を考えるにも一行問題はうってつけなので、ていねいに解いていってください。
==============================================================
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
通塾回数
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
容積の問題
==============================================================