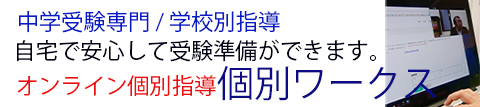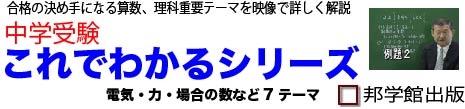■ ある先生は、「受験生なんだから子どもがしっかり自分の時間を管理していかないといけない。だから時間管理の主権は子どもに持たせなければいけないのです。」と言われます。ところが親の立場からすると「そんなことしてたら、ウチの子はずっとゲームしてばかりになる。そんなことでは宿題すら間に合わない」ので時間管理の主権は親が持つべきだと考えます。
■ これ、どちらも正しいのです。確かに受験生の意識として自分で自分の時間を管理できるようにならないといけない。ただこれは精神年齢の高い子でないとなかなかできない。今の子どもたちは大人がいろいろ手を出しているので、まだまだ幼い。幼い子は、自分のやりたいことに優先順位が来るから勉強まで手が回りません。
■ しかし、親がすべて管理しようとすると、成長途上の子はいろいろと反発が始まる。それを力で押さえつけようとすればいろいろバトルが展開する。子どもだから親の言うことは聞くべきだ、はダメです。今の時代は明確にハラスメントになる。
■ ではどうするのか?
■ 親が基調を考えつつ、最終的に子どもが自分で決めるように仕向ける、ということです。ここで当然またいろいろあるでしょう。ただし、ここで親がとらなければいけない態度は一つ。「あなたが決めたのだから、結果苦労してもあなたが自分でがんばりなさい。」です。例えば勉強する時間になった。本人と話し合って、ここは勉強することになっている時間です。「勉強する時間になっているよ」とは言う。しかし、それ以上やらなくても、それは仕方がない。そこでいろいろバトルが始まれば親子関係が崩壊します。
■ 親子関係は崩壊させてはいけません。これは絶対、親も子も守らないといけないこと。家族として生活しているのだから、そこはもちろん優先しないといけない。土台、中学受験はみんながやらなければいけないことではないのです。
■ で、最終的に子どもはその子、その子の成長度合いによっていろいろ変わってきますから、それを見ていることが大事。ただ、精神的に大人にしていくために、いろいろ自分でやらせるようにしていくことを忘れないでください。
■ 朝、自分で起きない子に時間管理をさせるのは難しい。だから親がやる、ではなく、まず自分で起きるようにすることが必要なのです。
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
入試方法の変革期が来るか
算数オンライン塾
3月10日の問題
【塾でのご利用について】
フリーダムオンライン WEBワークス OEMのご案内