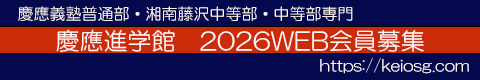受験層が絞られてきて、次のような構成比になると、およそ2倍の倍率に収束します。
合格可能性が80%以上の生徒が40%
合格可能性が50%程度の生徒が50%
合格可能性が20%程度の生徒が10%
例えば定員300人の学校があったとして、120人は合格可能性が80%以上とすると、合格可能性で割ると受験生としては150人ぐらいいることになります。
同様に合格可能性50%の生徒が150人いて、受験生はおよそ300人。
合格可能性20%の生徒が30人いて、受験生が150人。合計600人だから、ここでおよそ倍率が2倍になのです。
ということは、競争率3倍は状況が変わる。
合格可能性80%以上の生徒が20% 50%程度の生徒が50%、20%程度の生徒が30%とすると
300×0.2÷0.8+300×0.5÷0.5+300×0.3÷0.2=75+300+450=845人となって競争率が2.8倍ぐらいになる。
受験の実感としてはこのくらいの学校が多いのではないか、と思います。だから僅差になる。
合格ライン前後という競争が一番大変になるわけです。
で、ここを突破するためには、やはり正確さ、ていねいさが物を言う。
入試結果を見せてもらうと、1点違いで10人ぐらいは平気で違ってくるのです。なので、これからはとにかく正解率を上げる必要がある。
つまらないミスをいかになくすか。特に算数では1問の配点が多いので、計算問題だけで3~4点すぐに違ってきます。
ていねいに、ていねいに解いていきましょう。
11月23日の問題(規則性)
1週間無料公開されています。