授業の復習は必ずした方が良い、というお話をするのですが、最近は復習をさせない塾もあるようです。
というか、こういう塾は家で勉強しなくていい。つまり勉強はすべて塾でやる。つまりこれまで家でやっていたようなこともすべて塾に持ち込んで、先生の管理下の元でやらせる。
過去問もそうだし、問題集もそう。で、当然のことながら、これは先生の指示でやる。あれをやりなさい。これをやりなさい。やるとまた次の課題が渡されるというようなシステム。
ただ当然のことながら、塾に行っている時間が圧倒的に長い。週5日は当たり前。もしかするとほぼ毎日みたいな感じかもしれません。
こういう塾が出てきたのは、やはり少子化のせいもあるのです。各学年に十分な生徒数がいれば、やはり教室を回転させるから、当然週3日とか週2日ぐらいになるわけですが、そうでないから教室が空く。
空くのならそれを埋めないといけないから、通塾回数を増やす。今まで家でやらせていたことも塾でやることで、売り上げを確保しているようなところがあるわけです。
で、当然いろいろ問題もある。例えば、家でご飯が食べられない、家族の時間がない、などですが、一番いかんなあと思うのは、つねに指示されているところ、なのです。
自分の現状がこうで、何を変えなければいけないから、こういう段取りで勉強しよう、みたいなことは何も考えなくていい。だって先生が指示するわけだから。
だからいつまでたっても問題解決能力が育たない。こういう子が中学に入るとまた塾を探すしかなくなるわけです。
してあげることが多くなれば、自分でできることが少なくなる、ということはこういうところにも出てくるのです。
============================================================
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
学校を休む子
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
普段から見ているようで
==============================================================
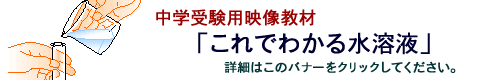
==============================================================

==============================================================

==============================================================
![]()
にほんブログ村
