同じ学年であっても確かに1年間の差があるわけです。その学年は4月2日誕生に始まり、次の年の4月1日生まれまでですから、確かに1年の年の差がある。
そうなると早生まれのお母さんは、「やはり早生まれだから・・・。」と何かと気にするかもしれません。
しかしながら、1年ぐらいの差は子どもの成長の仕方によってあっという間に埋まってしまうものです。実際に1つ下の子どもの方ができる、なんてことも当然あるわけで、これは気になるかもしれないが、気にしない方が良い。
むしろいろいろ手を出してしまうことによって、本人が自分でやらないようにしてしまうことの方が、影響が大きいと思います。早生まれだから、手伝うのではなく、どんどん自分でやらせる。
最初からうまくいくわけはありませんが、それでも褒めて具体的に指示をして、自分でできるようにしていく。
本来は部屋の掃除や洗濯物の片付け、あるいはプリントの整理、というようなことをひとつひとつ自分で解決できるようにしていくのが良いのです。
親は何かと心配が先に立ちますが、心配だからこそ自分でさせるように仕向けることの方が成長を促すことができるのです。もちろんよく見ていないといけませんが、手を出すのを少しずつ控えるようにしてください。
============================================================
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
叱る→ふてくされる→さらにやらない→叱る
==============================================================
今日の慶應義塾進学情報
慶應湘南説明会日程
==============================================================
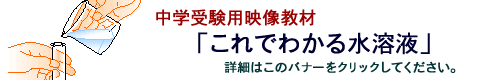
==============================================================

==============================================================

==============================================================
![]()
にほんブログ村
