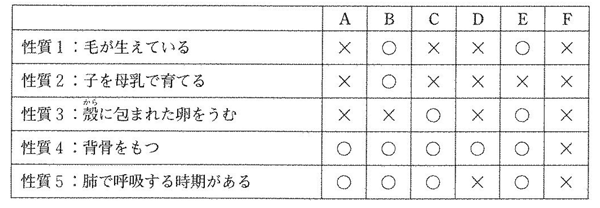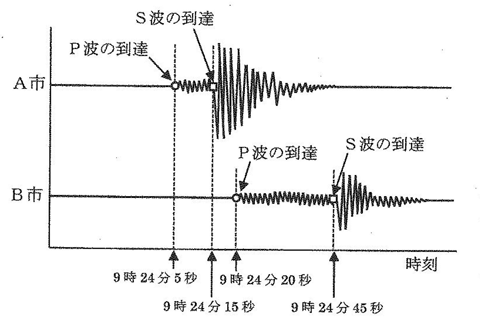2017年芝中学の問題です。
次の文を読んで、後の問に答えなさい。
セキツイ動物の進化は、水中から陸上への進出とともに大きく進んできました。陸上では水中とは異なり、からだが①乾燥します。②温度変化が激しいため体温を保つのも大変です。また、③水の浮力がない環境で重いからだを支えるため、骨組みとなるようなしくみが必要になりました。次の表は、ある動物A~Fが進化の中で身につけてきた性質を表したものです。
(1)動物A~Dが動物Fから進化してきたとして、動物A~Dを進化した順にならべなさい。
(2) 動物Aにあてはまる生物を、すべて選んで記号で答えなさい。
(ア)イカ (イ)ネズミ (ウ)イワシ (エ)カエル (オ)クジラ
(カ)イモリ (キ)ニワトリ (ク)へビ (ケ)アリ (コ)ワシ
(3)表の性質1~5の中で、下線部①、②へ適応するための性質として最も適当なものを、1つずつ選んで番号で答えなさい。
(4)下線部①について。水の浮力がない環境でヒトは直立二足歩行をするようになりました。次の各間に答えなさい。
(あ)直立二足歩行を行うと、重い内臓を支えるいくつかの骨が必要になりました。その骨の集まり全体の名前をひらがなで答えなさい。
(い)「ヒトが直立二足歩行を行うようになったために変化したこと」はいくつかあります。それとは無関係なことを次の中から2つ選んで記号で答えなさい。
(ア)歩行に前足を用いる必要がないため、物をつかんだり、道具を使えるようになった
(イ)二足歩行を行うときにからだのバランスをとるため、2つの目が頭の前方についた
(ウ)脳を首の骨で支えることができるため、脳が大きくなった
(エ)全体重を支えるため、足の裏が広く、かかとの骨が大きくなった
(オ)二本の足で歩きやすいように、つめが平らになった
(5)下線部③について。水の浮力がない環境で、植物はからだを支えています。そのために、茎の中のある2種類の管の集まりが役立っています。次の各間に答えなさい。
(あ)その菅の集まりの中で、内側にある管の名前を漢字で答えなさい。
(い)(あ)で答えた管のからだを支える以外の役割を答えなさい。
【解説と解答】
(1)A 両生類 B ほ乳類 C は中類 D 魚類
(答え)D→A→C→B
(2)両生類です。
(答え)エ,カ
(3)乾燥から身を守るために卵に殻がつきました。温度変化に対応するために毛が生えました。
(答え)① 3 ② 1
(4)(あ)骨盤です。(い)目が前にあること、つめが平らになったことが違います。
(答え)(あ) こつばん(い) イ・オ
(5)(あ)内側ですから道管です。(い)水分が通ります。
(答え)(あ) 道管(い) 根から吸い上げた水や肥料が通る。
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
すべて消さない
5年生の教室から
負担を減らそう
今日の慶應義塾進学情報
スケジュールを見直す