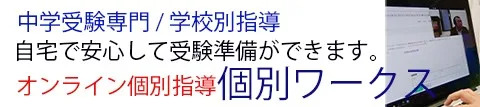これから大変なことは多くなるのですが、大事なことは基本に徹するということ。
特に6年生の理科は、計算問題が続いています。これはカリキュラム上仕方がないところがあって、算数で比と割合を習ってからでないと、うまくいかない。
その分、ずっと理科計算が続く。電気、中和、気体の発生、そして力のつりあい。
力のつりあいなど、レベルによっては、相等難しくなります。
ただ、これが全員に必要かと言われればそうではない。
だから学校別対策を始めるまでは、基本に徹することが大事。
学校によって出題されないことは多いので、組み分けにとらわれず、基本はしっかりできているようにしましょう。
なに、基本ができていれば、それなりのクラスは維持できるはずですから。