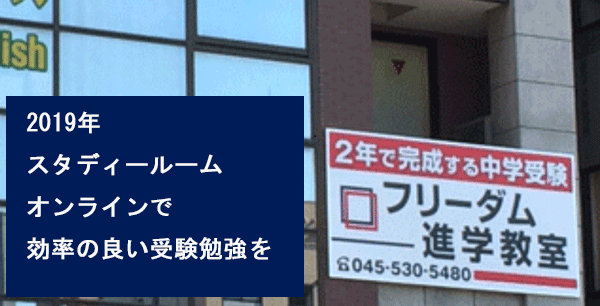6年生になると空間の把握に関する問題が出題されてきます。
立方体を切断したり、三角形をまわして回転体にしたりということなのですが、空間のイメージがわかない子が案外多いものです。
この原因を探ってみると、やはり図を書くのが下手な子という特徴があがってきます。小さい頃からあまり図や絵を書かなかった子が、空間をしっかり把握できないようなのです。
ためしに立方体の見取り図を書かせてみてください。本来ならば3種類の平行線で描けるわけですが、この線が平行でない子が多いのです。だから立方体がゆがみます。その意味ではやはり、小さいときから図や絵を書く機会をなるべく持たせてください。
私は受験後半を除いて、なるべくホワイトボードに問題を書いてノートに図を写させます。問題を写すという作業は、なかなか子どもたちにとっては大変なことなのですが、しかし、そうしないとなかなか図がかけない。グラフなどにいたっては、やはり真似て描くというところから覚えるので、板書を写すという作業は非常に大事な過程なのです。
自宅で問題を解くときも、なるべく自分で図を描く工夫をしてみてください。
Newフリーダム進学教室からのお知らせ
春期講習のお知らせ
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
作業をいとわない
5年生の教室から
算数のノートのポイント
算数オンライン塾
3月24日の問題
新4年生の保護者のみなさまへ 中学受験パパママ塾「ONE」のご案内