普通に考えると、子どもたちの各教科の偏差値がどれも同じ、ということはあり得ない。
つまり算数が良いが、国語が悪いとか、理科が悪いが社会は良い、というようなことが起こるわけです。しかし、最終的に4教科総合の偏差値で並べられると、その偏差値のでこぼこが無視されることになる。
クラス分けテストであるクラスに入ったときに、算数はカンタンだが、国語は難しい、というようなことが起こりうるわけです。
でも、そういうことは一切無視されている。科目別にクラスを分ける、ということをやっている塾はまずないでしょう。だから実際にはそういうでこぼこが日常からあるわけで、子どもたちの勉強が効率化されている、とまでは言えないのです。
で、そうなると、カンタンだと思うものは、もっと自分で鍛えなければいけないし、難しいと思うものは自分でもう少しやさしいところを勉強しないといけない、というようなことが起こってくる。それを何から何までやるような時間はありません。
なので少なくとも基礎をもう少しやっておく、ということに比重を置くべきでしょう。クラスで学習する内容がまあ、やさしいな、と思うのであれば、それはそれでいい。
しかし、これは難しい、と思ったことはもう少しかみ砕いて勉強しないといけないところがあるわけです。それをやっていないと、先先、大きな穴が開いてきます。その穴を埋めるのは大変なことなので、できる限り今のうちに手を打っておきましょう。
============================================================
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
個の勉強
=============================================================
中学受験 算数オンライン塾
4月8日の問題
==============================================================
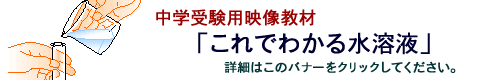
==============================================================

==============================================================

==============================================================
![]()
にほんブログ村
