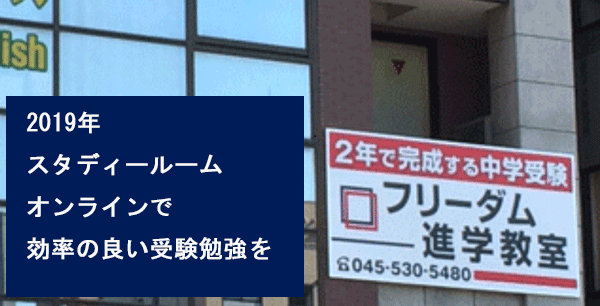難しい問題を解き上げるためには、じっくり時間をかける必要があります。
最初からスラスラ解けるわけではないから、その分考えないといけない。そのために、いろいろ手を尽くすから当然時間がかかるでしょう。
しかし、その時間をかけないとできるようにはならない部分があります。ただ、解答、解説を見たからといってそれでできるようにはなりません。
一方、試験を受けるとなると、最初から時間が制限されている。だから、難しい問題にかかってはいられない。まずは、自分が簡単に解ける問題から、というのはわかっているのですが、しかし、簡単に解けると思ったものが、解けない場合もある。
それでいろいろ時間をつかってしまって、点数がまとまらない、ということもあるでしょう。
これはこれで練習をしないといけないところはあります。
難しい問題を解く練習、時間内に問題を解き上げる練習、は基本的に別の訓練だと言えます。
時間内に問題を解き上げる練習ばかりをしていれば、難しい問題をじっくり考える力はつかない。
土台、現在の塾の組み分け試験は、難問を少なく出す学校の出題形式とは全く違うでしょう。その点数が悪いからといって、志望校の合否も難しいと判断することはあまり得策ではありません。
受ける学校によって、その練習の割合は変わるべきだと思います。例えば問題量の多い学校を受験する場合は、時間内に解き上げる練習をした方が良いが、難しい問題が少なく出る学校に対しては難しい問題を解きあげる練習は不可欠であり、それをやらないとできるようにはなりません。
組み分け試験というのは、ひとつの試験で順位をつけてしまうので、その辺が見えにくくなる。これは摸擬試験でもそうです。元々、1種類の試験ですべての学校の合否判定を出すこと自体は無理な話ではあるものの、やらないといけないから統計の手法を使っているに過ぎない。
まずは志望校を決めたところで、どちらの練習に比重を置くのがしっかり決めていきましょう。
Newフリーダム進学教室からのお知らせ
春期講習のお知らせ
受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
面倒な出題
6年生の教室から
テストを見直す
算数オンライン塾
3月6日の問題
新4年生の保護者のみなさまへ 中学受験パパママ塾「ONE」のご案内